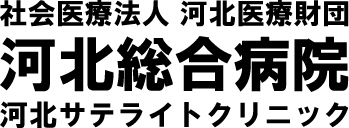臨床工学科の主な役割
臨床工学技士は、医療機器を保守・点検・管理・操作をおこなう医療技術者です。医療機器には、人工透析(血液浄化療法)・人工呼吸器・人工心肺装置など医師の指示のもと操作する生命維持管理装置などがあります。その他、日常的に使用している医療機器(輸液ポンプ・血圧計・生体情報モニタなど)も安全に使用できるよう点検・修理し、安全性確保と有効性維持に貢献しています。また、安全に使用するための教育も定期的におこない、医師・看護師・その他の医療従事者のサポートをします。
臨床工学科の主な業務
血液浄化(外来・入院)
血液浄化療法は、血液内の毒素を除去する治療です。一般的に知られている維持透析治療は、外来透析では河北透析クリニック、入院透析では河北総合病院 透析室でおこなわれています。業務の一環として透析患者さんの命綱であるバスキュラーアクセス管理や安全な透析をおこなう要となる透析液の清浄化を日本透析医学会の基準に基づきバリデーションによって高い清浄度で管理をおこなっています。河北総合病院 透析室では維持透析治療以外の血液浄化療法として、薬物治療では治療が困難な膠原病や神経免疫疾患、血液疾患、閉塞性動脈硬化症、一部の皮膚疾患、潰瘍性大腸炎などに対しアフェレシス療法(血漿交換・吸着療法・腹水濾過濃縮再静注など)を施行しています。またICU・CCUで治療中の重症感染症や心不全をともなった多臓器不全患者さんに対し、集中治療の一環として間欠的あるいは持続的な急性血液浄化療法をおこなっています。どの治療においても、治療の準備から終了までその専門的な知識・技術をもって対応しています。
心臓カテーテル検査室
心臓カテーテル室では、狭心症や心筋梗塞といった心臓血管疾患や腹部・下肢の閉塞性動脈硬化症(ASO)などの検査や治療に対し、ポリグラフの操作や解析、CMD測定のセッティング、IVUS/OCTなどの画像診断装置の操作などをおこなっています。頻脈性不整脈に対し、電気生理学的検査や、カテーテルアブレーション治療では、心臓電気刺激装置・3Dマッピング装置(EnSiteシステム)・CRYOConsoleの操作および管理などをおこなっています。頸動脈ステント留置術(CAS)や脳動脈瘤コイル塞栓術などの脳内科領域、経皮的バスキュラーアクセス拡張術(VAIVT)などの透析領域でも積極的に準備・介助をおこなっています。また、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、経皮的心肺補助装置(PCPS)などの機器操作および管理もおこなっています。
手術室(人工心肺操作含む)
手術室にある機器を管理しています。現在の手術環境では医療機器を使用しないと成り立たちません。ロボット手術装置も導入され、より高度な手術、専門知識の必要な医療機器が多く扱われる手術室では臨床工学技士の役割は大きいです。当院では、各手術室の準備(麻酔器の始業点検含む)や、開心術での人工心肺装置の操作、鏡視下手術の準備・介助もおこなっています。自己血回収装置、手術用顕微鏡やナビゲーションシステムなどの手術支援装置の操作、管理も実施しています。臨床工学技士の業務の一部改正を受け、当院でも呼吸器外科をはじめとしたスコープオペレーター業務にも着手しています。また、手術で使用したビデオスコープや硬性・軟性鏡などの滅菌機器の滅菌前点検を日常的におこない、手術室運営が円滑におこなわれるよう調整しています。
心臓植え込み型デバイス(外来・入院・手術立会い)
体内に植込まれているペースメーカなどの状態・情報を「プログラマー」と呼ばれる機器を操作し、医師へ報告する業務をおこなっています。定期検査外来・植込み手術・植込み患者さんの他手術時の設定変更・MRI撮像時の設定変更などに対応しています。また、専用ネットワークを用いた植込みデバイスの遠隔モニタリングの管理をおこなっており、医師と連携しながら、患者さんのサポートに取り組んでいます。
人工呼吸器管理
人工呼吸器は、呼吸障がい・不全(自発呼吸では酸素を十分に取り込めない、換気が不足する)に対して呼吸の補助や代行をする機器です。主な使用目的は、①肺のガス交換異常の是正、⓶肺容量の増加、⓷呼吸仕事量の軽減の3つです。これらを使用する場所は、重症患者さんに対し集学的に治療をおこなう集中治療室、全身麻酔によって外科的・内科的に手術をおこなう手術室や心臓カテーテル室、慢性的に呼吸補助が必要となった患者さんをケアするための一般病棟、引いては退院後生活をされるご自宅や施設など多岐にわたります。
臨床工学科としての主な活動は、一般病棟や集中治療室において人工呼吸器管理中の患者さんに機器が適正に使用されているか、各患者さんを巡回し毎日点検をおこないます。患者さんの状態と人工呼吸器の換気条件の双方から確認し、医師や看護師と連携をとりながら管理しています。また、装着時の介助から、院内移動、ベッドサイドへの設置、トラブル対応なども担っています。取り扱う機器は、気管挿管チューブ等などの人工気道を使用して換気をおこなう侵襲的陽圧換気(IPPV)、気管挿管をせず口や鼻に装着したマスクを通して換気をおこなう非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)、酸素療法の一環である鼻腔へ高流量の加湿された酸素を投与する高流量鼻カニュラ酸素療法(HFNC)などとなります。また、継続的に人工呼吸器が必要となった患者さんに対し在宅用人工呼吸器の装着や取り扱い説明、業者とのやり取りなどにも介入し、スムーズな移行のサポートをおこなっています。これらの人工呼吸器の導入から使用後までを管理や定期的な機器点検をおこない、次回使用のための安全の確保にも努めています。
機器管理
院内で使用される生命維持管理装置をはじめとした約5000台以上の医療機器を中央管理しています。日々、使用後点検・定期点検等をおこない、医療機器が安全に使用・管理できるよう努めています。また、院内機器トラブル、破損に対し点検・修理対応もおこなっております。メーカー主催技術講習を受講することより機器に対し精通し、メーカー修理依頼が必要な機器も院内修理対応を可能としています。
災害医療
当院は杉並区に8施設ある災害拠点連携病院の1つです。臨床工学科としては部署内でのアクションカードを用いた災害訓練を定期的に開催しています。また、院内だけでなく行政や区内透析施設と連携し災害時透析医療継続に向けた訓練をGoogleDriveを用いた患者マッチングシステムで実施しています。
医療安全
2007年の医療法改正にともない、「医療機器の安全な操作と管理」が、良質な医療を提供する体制の確保するための施策の一つとなり、生命維持管理装置や各種医療機器を駆使した治療の、質向上と安全確保をすることは、臨床工学技士としての責務となりました。
これにより、これまでの医療機器管理や教育・研修だけでなく、医療安全科と連携し、院内および他施設におけるインシデント・アクシデントの分析情報を共有し、院内における医療機器をとりまく安全体制を構築に努めています。また、臨床工学科内では、危険予測など医療安全に関するトレーニングをおこなっています。
医療機器に関する勉強会
様々な医療機器を使用するのは、各スタッフ自身です。全スタッフを対象に、医療機器を安全・確実に操作していただけるよう院内での勉強会を医療機器メーカーとも協力して積極的におこなっています。また今年度から動画資料を整備・作成して定期配信して、院内全スタッフにME機器に関する知識向上・操作手順や知識の再確認もおこなえる環境を整えています。さらに、より専門性を要する機器に関しては、該当部署に対して機器の説明のみならず周辺知識も含めた勉強会を実施するよう努めています。多岐にわたる専門領域での業務に対応するため、日々科内でのトレーニングで振り返り勉強会を実施しています。
所属長からのメッセージ
現在の医療において医療機器はなくてはならないものとなり、重要な役割をもっています。機器の管理および使用方法によっては重大な事故を引き起こす可能性もあるため、点検・修理などの管理や、使用する医療従事者への教育・サポートも重要な業務です。機器を通じてチーム医療に貢献し、質の高い医療を提供できるよう努めています。新しい医療機器の隣には常に私たち臨床工学技士が寄り添っています。
スタッフ紹介
医療技術部副部長
松島 茂嘉
認定/資格 臨床工学技士 科長
田中 光生
認定/資格 臨床工学技士 副科長
小幡 亜妃
認定/資格 臨床工学技士
専門外来
実績
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 血液浄化専門臨床工学技士 | 2 |
| 不整脈治療専門臨床工学技士 | 1 |
| 呼吸治療専門臨床工学技士 | 1 |
| 手術関連専門臨床工学技士 | 1 |
| 体外循環認定士 | 4 |
| 認定血液浄化臨床工学技士 | 3 |
| 認定集中治療臨床工学技士 | 3 |
| 認定医療機器管理臨床工学技士 | 1 |
| 透析技術認定士 | 10 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 6 |
| 心血管インターベンション技士 | 4 |
| 植込み型心臓デバイス認定士 | 2 |
| 周術期管理認定 | 2 |
| 日本アフェレイシス学会認定技士 | 1 |
| ME2種技術者 | 14 |
| 透析技能検定2級 | 5 |
| 心電図検定1級 | 1 |
| 心電図検定2級 | 2 |
| 心電図検定3級 | 3 |
| フットケア指導士 | 1 |
| 認定ホスピタルエンジニア | 1 |
| 医療機器情報コミュニケーターMDIC | 1 |
| 基本情報技術者 | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 1 |